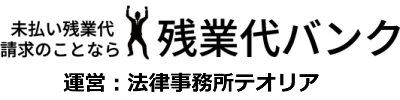2017/09/22
付加金が支払われる可能性は?期待してはいけない4つの理由
Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dawnraid/zangyou.org/public_html/wp-content/themes/elephant2/single.php on line 56

残業代請求について独自に勉強(インターネットで検索)した方の中には、「付加金も請求したい」という結論に行き着く方がいます。
「付加金」とは労働基準法違反に対する罰金のようなもので、その額は「請求金額と同一額」です。つまり、付加金が支払われれば「請求金額の2倍」を回収できるということになります(※詳細は後述)。
しかし、結論から言います。
残業代請求において付加金が支払われることは「ほぼ」ありません。
「支払われることはない」と断言はできませんし、(いわゆる裁判において)支払いが命じられたケースもあります。
ですが、心構えとしては、「支払われないもの」として捉えておくべきです。インターネットで検索した情報に煽られ、過度の期待を持ってはならないということです。
このページでは、「付加金が支払われることはない理由」と、「支払われないが請求はしておくべき理由」を解説していきます。
このページの目次
1.そもそも付加金とは?
まず、付加金とは何か?、法的根拠も含めてきちんと理解しておきましょう。
1-1.付加金とは?付加金の法的根拠
付加金とは、労働基準法に定められた罰則のひとつと捉えてください。
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
労働基準法第114条(付加金の支払)
1-2.付加金の支払いを命じられる使用者(会社)とは?
前記条文を読み解くと、付加金の請求を命じられる使用者は次の通りです。
1-3.付加金の額は?
これも前記条文を読み解くと、「使用者が支払わなければならない金額と同一額」です。
つまり、付加金が支払われるということは、請求金額の2倍を回収できるということになるのです。
2.残業代請求において付加金が支払われることはない4つの理由
それでは本題に入ります。
残業代請求において付加金が支払われることが「ほぼ」ない理由は主に4つです。
2-1.【理由1】残業代請求において利用する裁判は主に労働審判手続きだから
裁判の種類と管轄
示談交渉(相手方との書面などによる交渉)で和解できなかった場合には、いわゆる「裁判」に移行し、その判断を司直の手に委ねることになります。
しかし、一口に「裁判」と言ってもいくつかの種類があり、残業代請求に馴染むものとしては「通常訴訟」「少額訴訟」「労働審判手続き」が挙げられます。
「労働審判手続き」の詳細は別の機会に解説しますが、このページでは「労働審判手続き=労働問題専門の簡易裁判のようなもの、且つ、かかる期間も4ヵ月程度と短いのもの」という理解で構いません。
ここでポイントになるのは、「通常訴訟と少額訴訟」と「労働審判手続き」では、その管轄者が異なるということです。
下表の通り、「通常訴訟と少額訴訟」は裁判所の管轄、「労働審判手続き」は労働審判委員会の管轄です。
| 種類 | 主な例 | 管轄 |
|---|---|---|
| 裁判 |
| 裁判所 |
| 労働審判手続き |
| 労働審判委員会 |
| その他 |
| 各機関 |
※上表はわかりやすく簡略化して表現したものですので本来の意味とは異なる箇所もあります。
「管轄」と「付加金の支払い」の関係
では、管轄が異なるとどうなるのか?
労働基準法第114条を思い出してください。
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
労働基準法第114条(付加金の支払)
「裁判所は付加金の支払いを命ずることができる」とはありますが、「(労働審判手続きを管轄する)労働審判委員会が付加金の支払いを命ずることができるかどうか」までは言及していません。
| 裁判所 | 付加金を命じることができる |
|---|---|
| 労働審判委員会 | 付加金を命じることができるか明確ではない |
「明確ではない」であり、「命ずることができない」ではありませんが、後述する理由なども勘案すれば、労働審判手続きにおいて付加金の支払いが命じられることはないという考えが一般的です。
(事実、労働審判手続きにおいて付加金の支払いが命じられたものはありません。)
このページでは解説の都合上、労働審判手続きも含めて「裁判」と表現しています。しかし、「裁判」とは「裁判所によって行われる判断」が略されたものですから、裁判所の管轄ではない労働審判手続きは厳密には「裁判」には含まれないとも言えます。※労働審判手続きも地方裁判所で行われるため尚更に混同されやすいですが。
![]() 「理由1での結論は、「示談交渉」や「労働審判手続き」で付加金を回収することはできないとなります。」
「理由1での結論は、「示談交渉」や「労働審判手続き」で付加金を回収することはできないとなります。」
![]() 「じゃあ、裁判(訴訟)すればいいってことじゃない?」
「じゃあ、裁判(訴訟)すればいいってことじゃない?」
2-2.【理由2】残業代請求における裁判の50%以上は「和解」だから
「和解」とは何か?
「和解」とは「示談交渉(当事者間での交渉)において、お互いが譲歩して解決すること」と理解している方が多いかもしれません。
しかし、裁判においても「和解」はあります。
「裁判において、裁判所(裁判官)がお互いの譲歩を促して解決に導くこと」も「和解」です。
そして、裁判所が譲歩を促しても解決に導けない場合、つまり、和解できない場合に限り、裁判所から「判決」が命じられるのです。
労働審判手続きにおいて、審判官(裁判で言うところの裁判官)が譲歩を促して解決に導いた場合は、和解ではなく「調停」と言います。
裁判における和解の割合は?
下表は、平成27年度の「労働に関する訴訟(第一審※後述)における終局区分(件数)」をまとめたものです。
| 訴訟総数 | 判決 | 和解 | 取下げ | それ以外 |
|---|---|---|---|---|
| 2,298件 | 664件 | 1,357件 | 167件 | 110件 |
※司法統計から引用
これによれば、訴訟総数の59.0%ほどが「和解」による終局(解決)です。
何らかの理由により取下げられたものを除けば、訴訟総数の63.6%ほどが「和解」による解決なのです。
ですから、前提として、裁判においても和解があり、むしろ、和解で解決する確率が高いということを知っておいてください。
「和解」と「付加金の支払い」の関係
では、和解で解決するとどうなるのか?
付加金は裁判所が命じるものでしたが、前記の通り裁判所が命じるのは「判決」であり、「和解」は裁判所が命じるものではありません。
なぜなら、裁判所に導かれた「和解」は当事者の自発的なものだからです。
わかりやすく言い換えるなら、「和解」は裁判所が命じるものではなく、当事者が当事者自らに命じるものだからです。
つまり、裁判所が命じるものではない「和解」において、付加金の支払いが命じられる余地はないという考えが一般的です。
![]() 「理由2での結論は、訴訟しても「和解」による終局(解決)では付加金を回収することはできない(「判決」を得なければならない)となります。」
「理由2での結論は、訴訟しても「和解」による終局(解決)では付加金を回収することはできない(「判決」を得なければならない)となります。」
![]() 「じゃあ、判決を得ればいいんでしょ?」
「じゃあ、判決を得ればいいんでしょ?」
※判決が狙って得られるものかどうかという点は度外視しています。
2-3.【理由3】「第二審」が終局するまでに未払い金が清算されれば、付加金の支払いは命じられないから
訴訟の流れ
まず、予備知識として、「第一審」や「第二審」を含め、訴訟の一般的な流れについて触れておきます。
- 第一審
- 裁判所:地方裁判所(もしくは簡易裁判所)
目的:事実の認定。
備考:判決に不服がある場合には控訴し、第二審(控訴審)に移行。
![]()
- 第二審(控訴審)
- 裁判所:高等裁判所(第一審が簡易裁判所であった場合には地方裁判所)
目的:事実の認定。
備考:判決に不服がある場合には上告し、第三審(上告審)に移行。
![]()
- 第三審(上告審)
- 裁判所:最高裁判所(第二審が地方裁判所であった場合には高等裁判所)
目的:第二審の判決に「憲法解釈の誤り」や「訴訟手続きの違反事由」などがないかの認定。※事実の認定はしない(第二審までにされた事実認定、つまり、判決に拘束される)。
第一審及び第二審を「事実審」、第三審を「法律審」と呼称することもあります。
「第二審」と「付加金の支払い」の関係
では、「第二審」が終局するまでに未払い金が清算されれば、付加金の支払いは命じられないとはどういうことか?
この場合、第二審で「付加金」の支払いが命じられることはありません。
これを不服として上告したとしても第三審で「付加金」の支払いが命じられることもありません。
つまり、相手方の立場で言えば次の通りです。
第一審で付加金の支払いが命じられたとしても、第二審が終局するまでに未払い金を清算してしまえば、第二審で付加金の支払いが命じられることはない(命じられたとしても、第三審で覆され、支払いは命じられない)。
※控訴が棄却されないという前提あり。
![]() 「……え?なにそれ?納得できないんですけど?」
「……え?なにそれ?納得できないんですけど?」
![]() 「私も疑問を感じますが、次項で判例法理(裁判所が示した判断の蓄積によって形成された考え方)を基にこの理由を解説します。」
「私も疑問を感じますが、次項で判例法理(裁判所が示した判断の蓄積によって形成された考え方)を基にこの理由を解説します。」
第二審の終局が意味するものと裁判所の判断
事実認定をする事実審は第二審までとお話しました。
第二審は第一審の続きであり(続審制※注)、第一審と第二審はひとつづきの係争であり、つまり、第二審が終局するまでは判決(裁判所からの命令)は確定していないということです。
- 続審制とは?
- 「続審制」とは、第一審の裁判資料と第二審で新たに収集した裁判資料の両方を基にするものです。この他に「覆審制」と「事後審制」があります。「覆審制」とは第二審で収集した裁判資料のみに基づいて裁判をやり直すもの、「事後審制」とは第一審の裁判資料のみに基づいて第一審の判決の当否を判断するものです。
この観点では、第三審(上告審)は「(第一審と第二審の)事後審制」と言えます。
この「第二審の終局」と「未払い金の精算」の関係について、2つの判例を例示します。
- 事実:
- A会社が、雇用するBに対して解雇予告手当を支給することなく一方的に解雇を通告したため、Bが訴えた。
- A会社は第一審の口頭弁論終結日までにBに対して解雇予告手当相当額を支払った。
- Bは解雇予告手当が不足している(付加金含む)としたが、第一審、及び、控訴後の第二審はこれを棄却した。
- Bは上告したが、原判決(第二審の判決)は正当とし、また、付加金についても請求できないとした。
- 裁判要旨(付加金について):
- 付加金支払義務は、使用者が予告手当などを支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものである。
- 使用者に労働基準法第20条の違反(解雇予告手当未払い)があっても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
最二小判昭和35年3月11日
- 事実:
- A会社が、雇用するBに対して、未払賃金債務額の確認を求め、訴えた。
- Bは、これに付加金の支払いも求め、反訴した。
- 第一審は、未払賃金債務額、遅延損害金額、及び、付加金(一部)を認容した。
- A会社はこれを不服として控訴し、且つ、第二審が終局する前にBに対して、未払賃金額及び遅延損害金額の全額を支払い、Bはこれを受領したが、付加金にかかる訴えは取り下げなかった。
- 第二審は、付加金の支払い義務も認容した。
- A会社はこれを不服として上告し、第三審は原判決(第二審の判決)は不当とし、付加金に係る部分の請求を棄却した。
- 裁判要旨:
- (前記「最二小判昭和35年3月11日」を参照したうえで)
- 第二審の口頭弁論終結前の時点で、A会社がBに対し未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したものであるから、もはや、裁判所は、A会社に対し、付加金の支払を命ずることはできない。
最一小判平成26年3月6日
![]() 「理由3での結論は、訴訟し第一審で付加金支払いの判決を得ても、第二審が終局する前に未払い金が清算されれば付加金を回収することはできないとなります。」
「理由3での結論は、訴訟し第一審で付加金支払いの判決を得ても、第二審が終局する前に未払い金が清算されれば付加金を回収することはできないとなります。」
![]() 「……え?なにそれ?会社側の専門家がそういう判例を知ってたら付加金を回収できる可能性なんてなくない?」
「……え?なにそれ?会社側の専門家がそういう判例を知ってたら付加金を回収できる可能性なんてなくない?」
2-4.【理由4】そもそも、支払いが命じられるか否かは裁判所(裁判官)次第だから
前記の理由3までの時点で、付加金が支払われる(回収できる)可能性は極めて低いとご理解いただけたと思いますが、最後に理由4として、そもそも論もしておきます。
もう1度、労働基準法第114条を思い出してください。
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
労働基準法第114条(付加金の支払)
「裁判所は付加金の支払いを命ずることができる」とはありますが、「命ずる」でも「命じなければならない」でもありません。
そうです、そもそも、支払いを命じるか否か?もいくらの支払いを命じるか?も、すべて裁判所(裁判官)次第なのです。
しかも、裁判官によって、その判断基準は異なります。
付加金の支払い命令に対する判断基準において、敢えて、両極端な裁判例を挙げてみます。
裁判所は、その違反の理由や程度などを総合的に考慮して、支払いを命じるか否か、支払いを命じる場合にはいくらの金額の支払いを命じるかを決定すべき。
支払いを命ずることが不相当であるとして支払いを命じないことができるが、特別の事情が認められない限り、未払い金と同額の支払いを命じるべき。
結果、支払いが命じられたとしても、未払い金額の30~100%と、その額にはかなりの幅が見られます。
もっとも、請求者側からすれば、前者(消極的な裁判例)の「裁判所は、その違反の理由や程度などを総合的に考慮して、支払いを命じるか否か、支払いを命じる場合にはいくらの金額の支払いを命じるかを決定する」と捉えておくことをお奨めします。
![]() 「理由4での結論は、理由1も理由2も理由3も非常に難関だが、それ以前に、そもそも裁判所が命令しなければ付加金を回収することはできない(その額すら裁判所次第)となります。」
「理由4での結論は、理由1も理由2も理由3も非常に難関だが、それ以前に、そもそも裁判所が命令しなければ付加金を回収することはできない(その額すら裁判所次第)となります。」
![]() 「……付加金を請求する必要はないということ?」
「……付加金を請求する必要はないということ?」
![]() 「請求する必要はあります。実際に支払われたケースもありますので。ただ、「ネット上に蔓延する誤解を招くような情報に煽られ、過度の期待を持ってはならない」という注意喚起をさせていただきたいのです。」
「請求する必要はあります。実際に支払われたケースもありますので。ただ、「ネット上に蔓延する誤解を招くような情報に煽られ、過度の期待を持ってはならない」という注意喚起をさせていただきたいのです。」
3.付加金が支払われることはほぼないが、請求はしておくべき理由
3-1.請求はしておくべきたったひとつの理由
前記の理由1~4をクリアできれば付加金を回収できるからです。
もっとも、相手方や裁判官などの外的要因に大きく左右されることから、あなたの戦術や努力でどうにかなるものではないということもご理解いただけていると思います。
しかし、万が一ということもあります。
冒頭でお話した通り、支払いが命じられたケースも少なからずあります。
ましてや、(様々な語弊や誤解を恐れず言うなら)付加金の請求は手間のかかるものではありません。
「訴状(労働審判手続きの場合には「申立て書」)」に、「付加金も請求する」旨の定形的な一項を加筆するだけです。
3-2.労働審判手続きの申立て時にも請求だけはしておくべきか?
はい、労働審判手続きにおいて付加金の支払いが命じられることはありませんが、請求だけはしておくべきです。
前記の通り、「定形的な一項を加筆するだけだから」という理由もありますが、もう1つ、きちんとした理由もあります。
除斥期間
再三ですが、労働基準法第114条を思い出してください。
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
労働基準法第114条(付加金の支払)
「付加金の請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない」と定められています。
このように定められた期間を「除斥期間」と言い、これは「権利を主張(請求)できる有効期間」のようなものです。
つまり、付加金の除斥期間は2年であり、労働基準法違反があった時から2年間のみ付加金を請求する権利があるということです。
「除斥期間」と「消滅時効」の違い
「2年」「請求する権利」と聞くと、「消滅時効(残業代を含めた未払い賃金の請求権は2年で時効によって消滅する)」と同じ意味に理解される方もいるかもしれません。
ですが、「除斥期間」と「消滅時効」は同じではありません。
特に注意しなければならないのは、「除斥期間」には中断がないということです。
「消滅時効」であれば、請求(催告)によって時効を中断(停止)することができますが、除斥期間を中断することはできません。
ですから、「労働基準法違反があった時」から「2年以内」に「訴訟」しなければ、付加金を請求する権利が無効になってしまうのです。
「除斥期間」と「労働審判手続き」
ここで問題となるのは、(前記の通り、厳密に言えば)労働審判手続きは訴訟(裁判)ではないということです。
![]() 「相手方との示談交渉や労働審判手続きを経ても解決できず訴訟したが、示談交渉や労働審判手続きの間に2年が経過してしまった場合、付加金を請求する権利がなくなってしまうってこと?」
「相手方との示談交渉や労働審判手続きを経ても解決できず訴訟したが、示談交渉や労働審判手続きの間に2年が経過してしまった場合、付加金を請求する権利がなくなってしまうってこと?」
![]() 「読者にもわかりやすい、説明チックな驚きをありがとうございます。
「読者にもわかりやすい、説明チックな驚きをありがとうございます。
……ですが、そのようなことになってしまっては本末転倒なのです。」
なぜなら、労働審判手続きの成り立ち(目的)は、「解雇や給料の不払など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決すること」であるからです。
よって、労働審判法には次のような救済措置が定められています。
- 労働審判手続きにおける労働審判(裁判で言うところの判決)に不服申立てがあり訴訟に移行した場合には、労働審判手続きの申立て時の請求内容が、そのまま、訴訟されたものと扱う。
ですから、労働審判手続きの申立て時に付加金も請求しておけば、労働審判手続き中に除斥期間の2年を経過してしまったとしても、付加金を請求する権利は無効にならないということです。
労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
労働審判法第22条(抜粋)
4.付加金に期待してはいけない4つの理由のまとめ
このページの内容、残業代請求において付加金が支払われることは「ほぼ」ない理由をまとめると次の通りです。
- 「示談交渉」や「労働審判手続き」で付加金を回収することはできない。訴訟(通常訴訟や少額訴訟など)するしかない。
- 訴訟しても「和解」による終局(解決)で付加金を回収することはできない。訴訟し、且つ、「判決」を得なければならない。
- 訴訟し第一審で付加金支払いの判決を得ても、第二審(控訴審)が終局する前に未払い金が清算されれば(支払われれば)付加金を回収することはできない。
- そもそも付加金支払いの判決(命令)をするか否かは裁判所(裁判官)次第。さらに、裁判所が付加金支払いの判決をしたとしてもそれが請求額と同一額(満額)であるとも限らない。
![]() 「「付加金を請求したい」「付加金を回収したい」とお考えの方にとっては悲報とも言える内容であるかもしれませんが、ネット上に蔓延する「付加金を請求して倍返しだ!」などの誤解を招くような情報に煽られ、過度の期待を持ってはなりません。
「「付加金を請求したい」「付加金を回収したい」とお考えの方にとっては悲報とも言える内容であるかもしれませんが、ネット上に蔓延する「付加金を請求して倍返しだ!」などの誤解を招くような情報に煽られ、過度の期待を持ってはなりません。
ひとつの注意喚起として受け止めてもらえれば幸いです。」
関連記事 - Related Posts -
- 2013/02/21
残業代って、何時間分から請求できるの?
- 2013/03/10
最低賃金制度についても知っておこう
- 2013/02/15
あなたが受け取れる残業代はいくら?初心者のための計算方法
- 2013/05/16
請求し忘れ注意!未払い残業代の「遅延損害金」と「遅延利息」の計算方法
最新記事 - New Posts -
- 2017/05/31
強い労働基準監督署が帰ってきた!300社以上のブラック企業名を公表中
- 2017/05/29
あなたに最適な残業代の請求方法は?複数の無料相談を使い倒せ!
- 2017/05/10
ネットで完結!残業代の請求書は電子内容証明で送る【e内容証明版】
- 2017/05/02
自分で送る!残業代の請求書(内容証明郵便)の送り方【郵便局版】