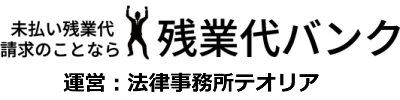2017/09/09
労働時間(残業時間)の定義を知っておこう
Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dawnraid/zangyou.org/public_html/wp-content/themes/elephant2/single.php on line 56

「残業代」を請求するには、「残業時間」を計算しなければなりません。
「残業時間」を計算するには、「労働時間」を計算しなければなりません。
つまり、残業代請求は「労働時間の計算」から始まると言っても過言ではありません。
ですが、使用者(会社)も労働者(あなた)もこの「労働時間」に対する認識が甘すぎます。
この甘さが未払い残業代を発生させる最大の原因です。
1.労働時間(残業時間)の定義を理解しよう
そもそも、労働時間とはどのような時間でしょうか。
通勤時間は含まれるのでしょうか?休憩時間は?出張先へ往復時間は?着替えの時間は?
これらも含めて、労働時間の定義を紐解いていきましょう。
実は、労働基準法においても労働時間の定義は明文化されていないため、判例(裁判例)などから解釈しなければなりません。
この解釈によれば、一般的には「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と定義されています。
この中でも特に「使用者の指揮命令下に置かれている時間」の定義がとても重要になります。
いわゆる手待ち時間(販売店で買物客が来るのを待っている時間、定時外の清掃時間、昼休み中に電話番をしている時間など)も使用者に義務付けられたものであれば労働時間に該当するということになります。
いくつか具体的なケースを例示すると次の通りです。
| 労働時間に該当するケースの例 |
|---|
|
| 労働時間に該当しないケースの例 |
|---|
|
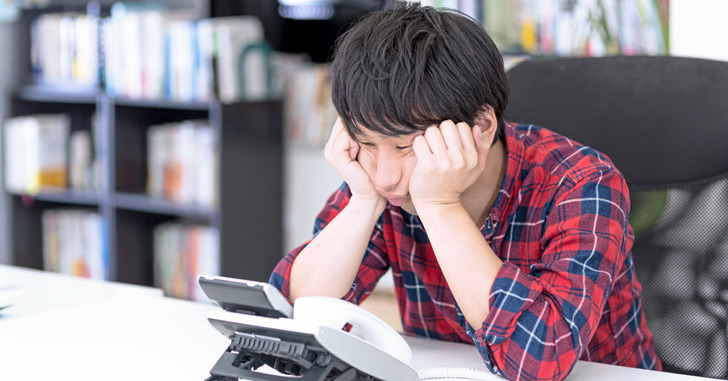
2.「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い
「定時」を法律用語で「所定労働時間」と言いますが、所定労働時間を超えただけでは割り増しされません。割り増しされるのは「法定労働時間」を超えた場合に限ります。基本中の基本ですので本項でサクッと理解しておきましょう。
2-1.法定労働時間とは?
労働基準法32条には次のように定められています。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(特例措置対象事業場においては44時間※注)を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法第32条(労働時間)
このように、法律で「原則、これ以上働かせてはいけません」と定められている(制限されている)労働時間を「法定労働時間」と言います。法で定められた労働時間だから、法定労働時間です。
特例措置対象事業とは、次の事業を営み、且つ、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満のものを指します。
商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店など。
特例措置対象事業場については『週44時間以上の特例措置対象事業場は残業代41万円以上の損!』で解説しています。
仮に、使用者と労働者の間で「1日の労働時間は10時間とする(10時間までは残業は発生しない)」というような雇用(労働)契約を締結したとしても、その契約は無効となり、法定労働時間の基準に置き換えられます。
なぜなら、労働基準法は「強行法規(※注)」だからです。
法律には「任意法規」と「強行法規」の2種類があり、労働基準法は「強行法規」です。
- 「任意法規」とは、当事者間の合意があれば、その法規(法律)に優先するルールを定めることができるものです。
- 「強行法規」とは、当事者間の合意があっても、その法規に優先するルールを定めることができないものです。厳密に言うと、優先するルールを定めることは自由ですが、そのルールは無効になります。
2-2.所定労働時間とは?
労働基準法によって「これ以上働かせてはいけません」という法定労働時間が定められているものの、すべての会社の定時(所定労働時間)が1日8時間、1週間40時間にて定められているわけではありません。
1日7時間労働であったり、7時間30分労働であったり、会社によってまちまちです。
このように、法定労働時間以下の時間数によって、会社ごとに定めている労働時間を「所定労働時間」と言います。
※所定労働時間が会社ごとにまちまちである理由は、このページの「3.いろいろな労働時間制度」にて解説します。
2-3.法定労働時間と所定労働時間は必ずしも一致しない
つまり、法定労働時間と所定労働時間は必ずしも一致するとは限りません。
この「法定労働時間」と「所定労働時間」が必ずしも一致しないことで気を付けなければならないのは、残業代の計算方法が異なるということです。
残業時間の賃金は25%割増という知識を持っている方は少なくありませんが、これは「法定労働時間」を超えた労働時間の賃金は25%割増ということなのです。
「所定労働時間」を超えただけの労働時間の賃金は割り増しされません。
例えば、所定労働時間が7時間である会社の場合、法定労働時間の1日8時間に至るまでの1時間(あるいは、1週40時間に至るまでの時間数)に対する賃金は、25%割増ではなく、0%割増(割り増しされない)となります。
3.いろいろな労働時間制度
前記の通り、労働基準法では原則的な法定労働時間が定められていますが、「1日8時間、1週40時間」という画一的な原則だけでは、会社の業種や、労働者の業務内容、雇用形態によっては効率的な労働を促進できない場合があります。
そこで労働基準法には、いわば画一的ではない労働時間制度も定められ、使用者が自分の会社に馴染む労働時間制度を採用し、不要な残業を削減できるよう配慮されています。
画一的ではない労働時間制度とは、大きく分別すると「変形労働時間制」と「みなし労働時間制」の2つです。
3-1.「変形労働時間制」の種類
変形労働時間制とは、予め、「一定の期間(1週間、1ヵ月、1年など)」と「特定の日または週」を定めておくことによって、その「一定の期間」内の1週間当たりの平均労働時間が法定労働時間(40時間、特例措置対象事業の場合は44時間)を超えなければ、「特定の日または週」において、法定労働時間を超えて労働させることができる(残業代も発生しない)という制度です。
うんちゃらかんちゃら……ちょっと難しいですよね。
法律というのは、堅苦しい用語ばかりを並べ、わざと理解しにくくしている(ような気がする)のです。
では、理解しやすいように、あなたが次のような会社の社長であるとしてイメージしてください。
- 月の上旬の忙しさは普通。法定労働時間内におさまる。
- 月の中旬は暇。法定労働時間では労働時間が余る。
- 月の下旬はすごく忙しい。法定労働時間内では到底おさまらない。
すると、敏腕カリスマ社長のあなたはこう考えるはずです。
そうです、お察しの通り、それを可能にするのが「変形労働時間制」なのです。
カリスマ社長は次のように設定しました。
特定の日または週: 月の下旬(実際には明確に定める必要あり)
1ヵ月における1週当たりの平均労働時間: 中旬と下旬で相殺して40時間以下
こうすることによって、月の下旬に1日当たり8時間や1週当たり40時間を超える日があっても、残業代が発生しない効率的な労働を促進することができるようになるのです。
さて、「変形労働時間制」のアウトラインを理解したところで、具体的な4つの制度を順に見ていきましょう。
- 1ヵ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
変形労働時間制1.1ヵ月単位の変形労働時間制
これは、正に前記のカリスマ社長のあなたが採用した制度です。
予め定める一定の期間が1ヵ月以内であり、その期間内の1週当たりの平均労働時間が法定労働時間(40時間や44時間)を超えないように、予め特定の日または週を定めておけば、法定労働時間を超えて労働させることができる(残業代も発生しない)という制度です。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出る、または、就業規則などに記載する。
- 各勤務日ごとの始業、終業時刻を明確に予め特定する。
- 変形の期間は1ヵ月以内とする。
- 変形期間の労働時間が、その期間の法定労働時間の上限(週法定労働時間×変形期間の日数÷7)を超えない。
- 変形期間の起算日を明確に特定する。
1か月単位の変形労働時間制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
法定労働時間を超えると特定されていた各日、各週、期間においては、その定められていた時間を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。
法定労働時間を超えないと特定されていた各日、各週、期間においては、法定労働時間(原則、1日8時間1週40時間)を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。また、前記の通り、所定労働時間外労働が発生している場合にも残業代(0%割増)が支払われなければなりません。
変形労働時間制2.1年単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制の、予め定める一定の期間が(1ヵ月ではなく)1年になったものです。
1ヵ月単位の変形労働時間制は月間で帳尻を合わせるものであったのに対して、1年単位の変形労働時間制は年間で帳尻を合わせるものです。
よって、時季(季節)によって業務量の繁閑の差が大きい会社で採用されていることが多いです。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 労働者の過半数を組織する労働組合(労働組合がない場合には過半数の代表者)との間で書面による協定を締結する。
- 1日の労働時間の上限は10時間。
- 1週の労働時間の上限は52時間。
- 対象期間が3ヵ月を超える場合はさらに次の条件を満たすこと。
(1)所定労働時間が48時間を超える週は、連続3週以下。
(2)3ヵ月ごとに区分した各期間における所定労働時間が48時間を超える週の初日は3回以下。 - 連続して労働させることのできる所定労働日数は6日。
- 特定期間の連続所定労働日数は、1週1日の休日が確保できる日数(12日)。
- 対象期間が3ヵ月を超える場合の所定労働日数の限度は1年あたり280日。
1年単位の変形労働時間制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
法定労働時間を超えると特定されていた各日、各週、期間においては、その定められていた時間を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。
※その期間における残業代は、その期間が終了した直後の給料日に支払われなければなりません。
法定労働時間を超えないと特定されていた各日、各週、期間においては、法定労働時間(原則、1日8時間1週40時間)を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。また、また、前記の通り、所定労働時間外労働が発生している場合にも残業代(0%割増)が支払われなければなりません。
変形労働時間制3.1週間単位の非定型的変形労働時間制
前記の「1ヵ月単位の変形労働時間制」の変則的なものですが、私はこの制度が採用されているケースに出合ったことがありませんから、多用されている制度ではないと思います。
予め定める一定の期間が1週間以内であり、その期間内の1週間当たりの平均労働時間が法定労働時間(40時間、特例措置対象事業についても同じく40時間)を超えないように、予め特定の日を定めておけば、法定労働時間を超えて労働させることができる(残業代も発生しない)という制度です。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、且つ、各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、常時使用する労働者数が30人未満の「小売業」「旅館」「料理店」「飲食店」。
- 労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出る。
1週間単位の非定型的変形労働時間制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
法定労働時間を超えると特定されていた各日においては、その定められていた時間を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。
法定労働時間を超えないと特定されていた各日においては、法定労働時間(原則、1日8時間1週40時間)を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。また、前記の通り、所定労働時間外労働が発生している場合にも残業代(0%割増)が支払われなければなりません。
変形労働時間制4.フレックスタイム制
ここまでの変形労働時間制とはまったく別物ですので、切り替えてお読みください。
フレックスタイム制とは、研究開発業務やデザイナー、設計業務など、労働時間を画一的に定めない方が業務効率が上がる職種に採用されることが多く、特定の場合において、法定労働時間(原則、1日8時間1週40時間)を超えて労働させることが認められる制度です。
また、出勤及び退勤の時刻は労働者自身が決めることができますが、「必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)」と、「その時間帯の中であればいつ出勤及び退勤しても良い時間帯(フレキシブルタイム)」とに分けられているのが特徴です。
なお、コアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムとすることもできます。

3-2.「みなし労働時間制」の種類
みなし労働時間制とは、予め、「労働時間数」を定めておくことによって、その労働時間数を労働したものとみなす制度です。
通常は、タイムカードや業務日報を基にして1分単位で労働時間を管理し残業代が支払われますが、例えば、外回りが主の営業職、思考が主の研究職など、実際の労働時間を管理(算定)することが困難である業務に採用されていることが多いです。
さて、「みなし労働時間制」には3つの制度がありますので、これも順に見ていきましょう。
- 事業場外のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
みなし労働時間制1.事業場外のみなし労働時間制
正式には「事業場外労働に関するみなし労働時間制」と言いますが、「事業場外のみなし労働時間制」と呼称されることが多いです。
外回りの営業職に代表されるような事業場外(会社外)で業務の全てまたは一部を行う形態で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定しづらいと判断される場合に、一定時間労働したものとみなすことができる制度です。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 事業場外の労働で労働時間の算定が困難な時は、原則として所定労働時間労働したものとみなされている(予め定める労働時間数が所定労働時間未満であるなど不当性がない)。
- 所定労働時間を超えて労働する必要がある場合は、その労働(業務内容)に通常必要とされる時間労働したものとみなされている。
- 上記の通常必要とされる時間を何時間にするか、労働者の過半数を組織する労働組合(労働組合がない場合には過半数の代表者)と書面協定を締結されている。
- 上記の書面協定にて定められている労働時間数が、法定労働時間を超える場合に限り、労働基準監督署に届け出ている。
なお、事業場外のみなし労働時間制が適法に採用されているかどうかを判断する最重要の基準は、真に労働時間の管理(算定)が困難であったか?です。
なぜなら、携帯電話の普及により、外回り中であっても使用者の指揮監督は及びますし、労働者がどこで何をしているか?の把握も困難であるとは言い得ないためです。よって、近年においては、事業場外のみなし労働時間制の採用が適法であると認められる職種や業務はごく限られたものになっています。
事業場外のみなし労働時間制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
「事業場外の労働時間」と、「事業場外ではない内勤の労働時間」を合算した時間が、法定労働時間を超えた場合には残業代が支払われなければなりません。
また、深夜労働や休日労働を行った場合には、本制度と関係なく、残業代が支払われなければなりません。
営業職の社員に対して「営業手当」などの名目の手当を支給し、残業代の支払いを勝手に免責している会社がありますが、これは「事業場外のみなし労働時間制」とはまったく関係ありません。これは俗に「みなし残業代制(定額残業代制)」と呼称される制度です。
繰り返しですが、事業場外のみなし労働時間制を適用するには、前記の条件を満たしている必要がありますし、近年においては、事業場外のみなし労働時間制の採用が適法であると認められる職種や業務はごく限られていますので、あなたに採用されている制度がどちらであるかは十分に検討してください。
※みなし残業代制が採用されていたとしても残業代が免責されることはありません。
みなし労働時間制2.専門業務型裁量労働制
特定の専門職において、一定時間労働したものとみなすことができる制度です。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出る。
前記の事業場外のみなし労働時間制は「事業場外(会社外)で業務を行う形態」というように「業務遂行場所」が限定されていましたが、この専門業務型裁量労働制は「業種」が限定されています。
下記の通り、システムの分析や設計、研究開発、デザインなど業務遂行の手段や時間配分などを労働者に委ねる必要がある業種に採用されます。
厚生労働省令及び厚生労働大臣告示が定める「業務遂行の手段や時間配分などを労働者に委ねる必要がある業種」の19業種(業務)
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 ※システムエンジニアは該当するがプログラマーは非該当
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
専門業務型裁量労働制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
深夜労働や休日労働を行った場合には、本制度と関係なく、残業代が支払われなければなりません。
みなし労働時間制3.企画業務型裁量労働制
俗に言うホワイトカラーにおいて、一定時間労働したものとみなすことができる制度です。
前記の専門業務型裁量労働制は「業務」が限定されていましたが、この企画業務型裁量労働制は「ホワイトカラー」に限定されています。
企画や立案、調査、分析など事業運営上の重要な決定が行われる事業所(本社など)で採用されることが比較的多いようです。
但し、この制度を適法に採用するには次の条件を満たしていなければなりません。
- 労働者について
- 客観的にみて、対象業務を適切に遂行するための知識や経験などを持っている。
- 対象業務に常態として従事している。
- 業務内容について
- 業務内容が、所属する事業場の事業の運営に関するものである。
- 企画、立案、調査、分析の業務である。
- 業務遂行の方法を大幅に労働者に裁量に委ねていて、業務の性質に照らして客観的に判断される業務である。
- 相互に関連しあう業務を、いつ、どのように遂行するかなどについての広範な裁量が労働者に認められている業務である。
- 手続きについて
- 労使委員会(※)を設置する。
- 労使委員会で5分の4以上の多数決議を取る。
- 労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出る。
※労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件に関する事項を調査審議し事業主に対して意見を述べる、使用者および労働者を代表する者が構成員となっている組織です。
企画業務型裁量労働制が採用されていたとしても、残業代が発生しないわけではありません。
深夜労働や休日労働を行った場合には、本制度と関係なく、残業代が支払われなければなりません。
4.重要なことは、あなたに採用されている制度は何か?を知ること
「法定労働時間」「所定労働時間」「いろいろな労働時間制度」について解説してきました。
法定労働時間や所定労働時間の定義は、すべての労働者が知っておくべき基本中の基本ですのでサクッと理解しておきましょう。
一方で、いろいろな労働時間制度は(正直に言うと)理解していなくても困りません。
なぜなら、すべての制度が採用されている人などいないからです。あなたに採用されているとしても、1つか2つです。
重要なことは、あなたに採用されている制度は何か?を知る(把握する)ことです。
そして、それが適法かどうかを判断することです。
「雇用契約書(労働条件通知書、採用通知書など)」と「就業規則」を確認すれば簡単に把握することができますので、『就業規則と雇用契約書』内の記事を参考にまずは把握に進んでください。
関連記事 - Related Posts -
- 2016/09/01
まだ損してるの?「実は労働時間に該当する」6つの事例
- 2013/02/19
そもそもサービス残業ってなに?当たり前だと思ってない?
- 2013/02/20
残業代が支払われる休日は?休日、休暇、休業、代休、振替休日の違い!
- 2013/02/15
あなたもチェック!未払い残業代のよくある悪質な10事例!
最新記事 - New Posts -
- 2017/05/31
強い労働基準監督署が帰ってきた!300社以上のブラック企業名を公表中
- 2017/05/29
あなたに最適な残業代の請求方法は?複数の無料相談を使い倒せ!
- 2017/05/10
ネットで完結!残業代の請求書は電子内容証明で送る【e内容証明版】
- 2017/05/02
自分で送る!残業代の請求書(内容証明郵便)の送り方【郵便局版】